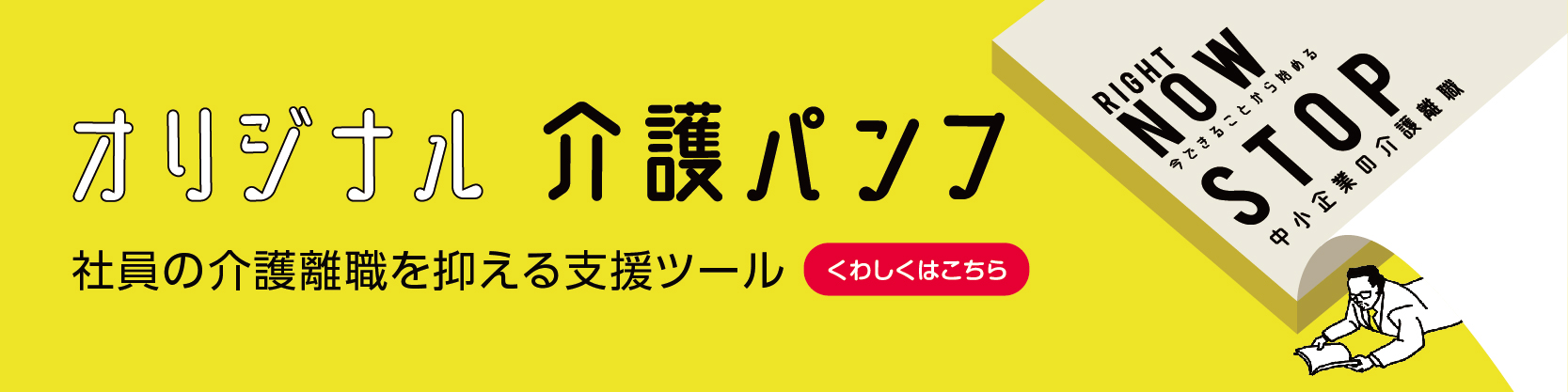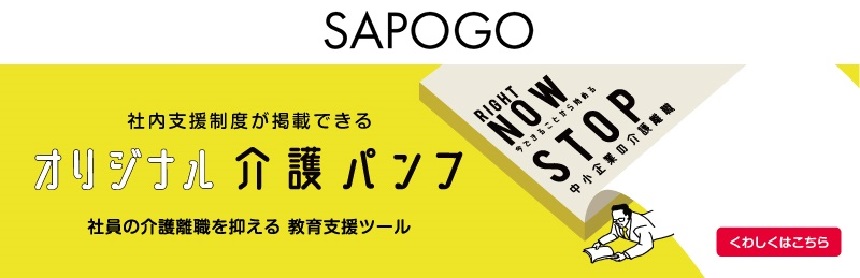超高齢社会に突入した日本。介護が必要な人が増えれば、必然的に介護する家族も増えます。75~85歳以上の世代の子供である40〜50代が該当するケースが多く、職場でも中心的な存在の彼らが仕事をしながら介護をする「ビジネスケアラー」になっていきます。
では、あなたの職場に「仕事と介護の両立をしている人」はいますか?「いない」「知らない」という人がほとんどではないでしょうか?
育児と違い、表に出にくい介護の話題
介護に関連する制度は「育児・介護休業法」ですが、同じ法律に規定されている「育児」と比べると、「介護」の当事者はかなり見えづらいです。「子どもが熱を出してしまって…」「保育園の送り迎えが大変で…」といった話題はよく耳にしますが「親の介護で…」「介護施設の手続きが…」といった話を聞いたことはありますか?
実は、介護と仕事を両立している人は決して少なくありません。しかし、多くの人がそれを周囲に話さず、1人で抱え込んでいるのが現状です。その結果、仕事との両立が難しくなり、最悪の場合は介護離職に追い込まれてしまうケースが増えています。
2030年には労働力人口の21人に1人がビジネスケアラーに
経済産業省の調べ(※)では、2030年には家族を介護する833万人のうち、約4割(約318万人)が仕事をしながら家族等の介護に従事する「ビジネスケアラー」になると予測され、これは労働力人口の21人に1人にあたるそうです。従業員200名の企業であれば社内に約10人のビジネスケアラーがいることになり、企業の介護離職防止対策は急務であることは間違いありません。
2025年4月から施工される「育児・介護休業法」の改正法では、従業員の介護離職を防ぐため、企業には以下の措置が義務付けられています。
・両立支援制度の利用促進
家族の介護が必要な従業員に対し、両立支援制度の個別周知や利用の意向確認を行うこと
・両立支援制度の社内浸透
家族の介護に直面する前段階(40歳前後)から、両立支援制度の情報提供や研修を行うこと
・介護休暇の取得要件の緩和
勤続6ヶ月未満の従業員も取得可能にすること
・家族を介護する従業員への措置の拡大
テレワークの追加(努力義務)
※ 2024年3月 経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より
介護離職を防ごうと思っても
しかし、国が「育児・介護休業法」の中身を充実させ、企業が支援策を実行したとしても、当事者が介護をしていることをオープンにしなければ、両立支援のスタート地点にも立てないのです。そして企業は「うちには仕事と介護を両立する社員はいない」と、本腰を入れて介護離職防止対策に乗り出さないでしょう。
本人が望まないなら無理に話す必要はない一方で、「話しやすい状況があるなら、相談してみたい。気持ちを誰かに聞いてもらいたい」と思っているのならば、言い出せない職場環境は健全な状態ではないでしょう。
育児は社会全体で支え合うものという認識が広がっていますが、介護については「個人的な問題」「家族の責任」と捉えられがちです。また、「迷惑をかけたくない」「辞めさせられるかもしれない」といった不安から、職場で介護のことを話しづらいと感じる人も多いのです。

介護を自分ごととして考えよう
介護は誰にでも訪れる可能性があります。家族の年齢構成や健康状態によっては、突然、介護の担い手にならざるを得ないこともあります。今は関係ないと思っている人でも、いつ自分ごとになるかわからないのです。
あなたの職場には、介護と仕事を両立している人がいるかもしれません。そして、話しづらさから1人で悩んで、疲れているかもしれません。まずは「何か手伝えることはありますか?」と声をかけてみることから始めてみませんか?