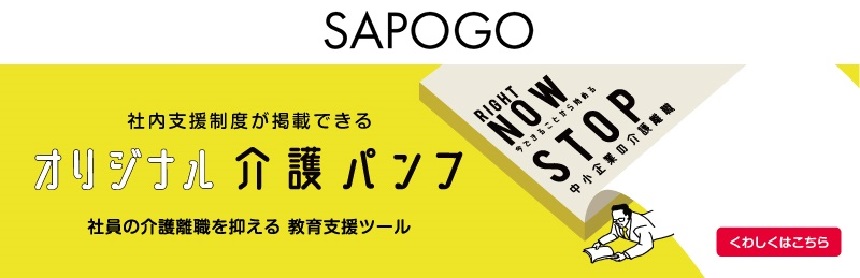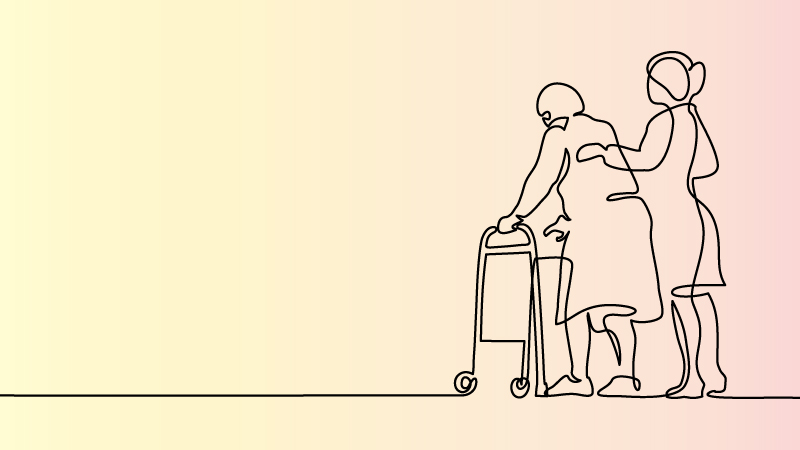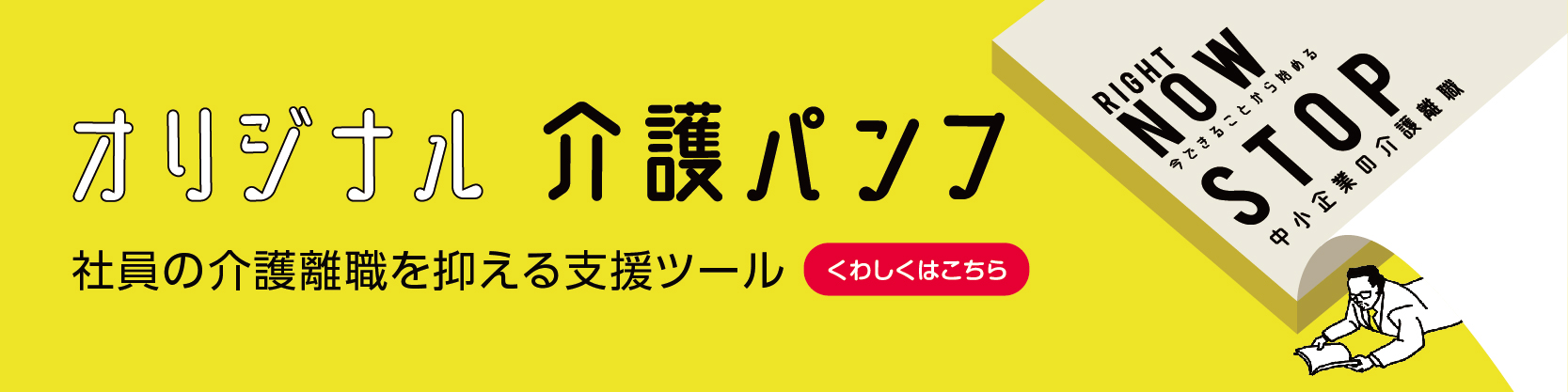親の様子が少しおかしいな、という段階で介護について準備する人は多いかもしれませんが、親が元気なうちに準備する人はあまりいないと思います。実際のところは、予測しない事故や脳血管疾患などで急に介護状態になる可能性は少なくありません。急な介護スタート慌てないように、今すぐできる簡単な事前準備2点をご紹介します。
むしろ、介護は急にはじまることが多い
厚生労働省の調査によると、介護や支援が必要となった主な原因の第1位は「認知症」ですが、割合的には全体の2割以下。次いで第2位「脳血管疾患(脳卒中)」第3位「骨折・転倒」と、予測できない病気や事故から介護がはじまるケースも多いことがうかがえます。
介護が必要となった主な原因(上位3項目)
1位 認知症 16.6%
2位 脳血管疾患(脳卒中)16.1%
3位 骨折・転倒 13.9 %
出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査介護の状況」
急な介護で慌てないために
介護は誰もが直面する可能性がありますが、親が元気なうちは話題にしづらいものです。急な介護でパニックにならないよう、介護する側ができる簡単な事前準備を2つをご紹介します。
1.親の居住地の「地域包括支援センター」を把握しておく
介護に直面した場合、「地域包括支援センター」に連絡すれば、介護認定の申請手続きや、受けられる介護支援サービスの情報を入手することができます。介護サービスの申請は「介護対象者本人の居住地」ベースになりますので、まずは親の住む地域の地域包括支援センターがどこにあるかと連絡先を把握しておきましょう。
※地域包括支援センターはエリアごとに(おおよそ中学校区)担当圏域が決まっています。
2.自分の勤務先の相談窓口を確認しておく
介護が始まったことを勤務先に報告する義務はありませんが、報告しないまま働き続ける「隠れ介護」が問題視されています。その背景には、「キャリアに影響する」「周りに迷惑がかかる」など理由は様々でしょう。しかし、2025年4月の法改正で、会社側も「介護に直面した従業員が申出をした場合、介護休業制度等に関する周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行うこと」が義務化されます。よって、従業員側から伝えることはより重要になってきます。
会社側も、介護が本格化する前から状況を把握することで、色々対策が立てやすくなります。
参照:
「隠れ介護」で急に介護離職される前に!周知するべき社内の両立支援制度
2025年 育児・介護休業法改正のポイントと企業がいますぐ準備すべきこと
1人で、家族内だけで抱え込まないこと
今回お伝えしたいことの要点は「介護は1人で、家族だけで抱え込まず、地域や職場のサポートを最大限に活用すること」です。早い段階からサポートにつながるために、地域と勤務先の相談窓口を把握しておくことはとても重要で、いますぐ確認できるとても簡単な第一歩になります。